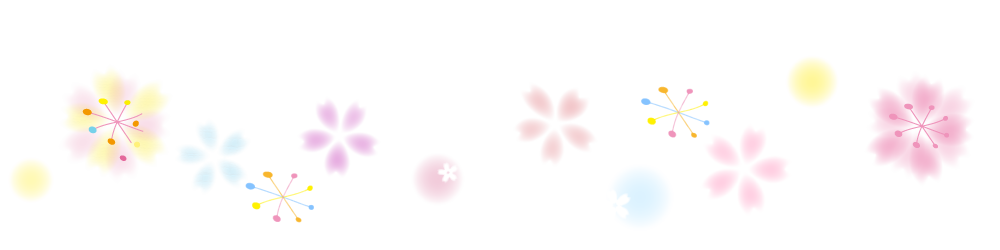海の近くで咲いている白い菜花のような植物は、ハマダイコン(浜大根)でした。
ハマダイコンは、思わず「大根の花~」と呼んでしまいそうな出で立ちです。
いつもダイコンバナと呼んでた花は、紫色。
でも普段食べてる大根の花は、白い花、もしくは薄い紫色の花。
なんだかちょっと混乱してしまいそうです。
もしかして紫色のは、花大根(ハナダイコン)?
間違えだったかもしれないと調べてみると、ハナダイコンは、紫の花を咲かせるけどハナダイコン属で別種。
そっくりさんには、ムラサキハナナとも呼ばれるオオアラセイトウ。
白い菜花のような植物は、ハマダイコン(浜大根)。
目次
ダイコン花? ハマダイコンの特徴や様子・オオアラセイトウとハナダイコン

春に海の側の空き地で見かけたハマダイコン。
アブラナ科ダイコン属の越年草。 小さな花びら4枚。
はまだいこん(浜大根)
わが国の各地に分布していますが、古い時代に渡来した「ダイコン」が野生化したものといわれています。海岸の砂地に生え、高さは30~70センチになります。葉は羽状に深裂します。4月から6月ごろ、淡紅紫色の花を咲かせます。根はあまり太くならず、食用には向きません。 引用:Weblio辞書
ハマダイコンの特徴

白地にほんのりとした淡い紅紫色が入っていて、優しい雰囲気がある花を咲かせます。
遠くから見ると、白い菜の花みたいにも見えます。
ダイコンが浜に自生するようになったと考えられたため、ハマダイコン(浜大根)の名がつけられました。
食用には不向きとありますが、根も葉も実(サヤ)も食べられるようです。
栽培のダイコンと比べるとアクや苦味が強いようです。
花言葉は、「ずっと待ってます」。
科・属名:アブラナ科/ダイコン属
学名::Raphanus sativus var. raphanistroides
英名: Japanese radish
草丈:30cm~70cm
開花時期:3月下旬~6月
生育場所:日本全土の日当たりのよい海岸沿い、他。
開花時期:3月下旬~6月
ハマダイコンのようす

花は直径2-3cmの十字形花。
花弁は4枚、離生。
白色で、緑から紫色の脈があり先端近くが紫紅色を帯びる。雄しべは6個、雌しべは1個。

上の方には蕾がたくさん。
下の方から開花していくようです。

咲き始めの蕾は、赤紫の模様が入っていて可愛らしい。

若い蕾や葉の様子。
葉は羽状分裂し、長さ5~20cm。

茎には、刺状の毛がある。

ハマダイコンの花は春の花。
黄色ければ、菜の花のような感じですね。
ムラサキハナナとも呼ばれるオオアラセイトウ

ムラサキ色のダイコンの花?
この花は、アブラナ科オオアラセイトウ属の越年草。 小さな花びら4枚。
- オオアラセイトウ(大紫羅欄花)
- ショカツサイ(諸葛菜)
- ムラサキハナナ(紫花菜)
などと呼ばれています。
春になると、庭や道端や空き地でもよく見かけます。
花言葉は「知恵の泉」「仁愛」「優秀」。
オオアラセイトウ(大紫羅欄花、Orychophragmus violaceus)は、アブラナ科オオアラセイトウ属の越年草。別名にショカツサイ(諸葛菜:諸葛孔明が広めたとの伝説から)、ムラサキハナナ(紫花菜)。 引用:Wikipedia
ハナダイコンとの違い?

オオアラセイトウもダイコンの花、ハナダイコンなどとも呼ばれてたりしますが、
花大根(ダイコンバナ)(英名=Hesperis matronalis)は、アブラナ科ハナダイコン属で、オオアラセイトウとは別の種類です。
シベリアから西アジア・ヨーロッパにかけてが原産地。
別名:ヘスペリス・マトロナリス。
オオアラセイトウとダイコンバナは、よく似てる花を咲かせるので、見分けにくいようです。
ダイコンバナは、分岐せず上部に咲く・葉に艶がないなどの特徴があるようです。
花言葉:「競争」。
菜の花

黄色い菜の花は、アブラナ科 アブラナ属。
菜の花とは、アブラナ属の植物の総称か、アブラナもしくはセイヨウアブラナの別名。
日本へは弥生時代に渡来したと考えられています。
菜の花は、「食用の花」という意味でつけられています。
「菜」という字は、食用を意味している。
また、観賞用は「花菜(ハナナ)」、食用は「菜花(ナバナ)」と区別して呼ばれてます。

黄色の十字状花は、蝶々みたいですね。
花言葉は、「快活」「豊かさ」「明るさ」他。
菜の花は、2月下旬から4月までが見頃です。
「ハマダイコン」も「オオアラセイトウ」、「ハナダイコン」、そして「菜の花」も春に咲くアブラナ科の植物。
みんな花びらが4枚の十字状花です。
アブラナ科の植物は、十字状花が特徴のようです。