初夏を彩る美しい蓮(ハス)の花。
花の中をゆっくり覗いてみると、そこには、『おやっ』て呟きたくなるほど、一目みたら忘れないほど不思議な空間が広がっています。
ハスの花の中ってどんな感じ? ゆっくり見てみませんか。
花が散ってしまい、実をつける様子も面白いです。
目次
ハスの花の中は、不思議がいっぱい。花托から果托へ

ハスは花の姿といい、葉の形といい、どことなく神秘的な感じが漂います。
なぜか興味深くなりませんか。

端正で優雅、浮世離れした美しさがあるハスの花。
しかし花の命は短くて、3~4日程で散ってしまいます。
ハスの花は、早朝に咲き始め、午後には閉じていく・・・3日~4日繰り返して、最後の日は閉じることなく花びらがパラパラと落ちていきます。
見に行くときは、早朝がおすすめです。
ハスの花の中はこんな感じ、

ハスの花の中。
大きな美しい花弁を開くと、色も形もかなり不思議な感じ・・・
神秘的な空間が広がっています。
花托
花の中央にある薄緑色の部分は、すこしふわふわっとしていて花托(かたく)と呼ばれているところです。
花托とは花床(かしょう)ともいいます。
花葉(かよう)を支えるところで、多くの花ではあまり目立ちません。
(花びら・雄しべ・雌しべ・萼 (がく) などがつく部分。)
雌しべ
そして、花托の表面に見える丸いぽちぽちが、ハスの花の雌しべです。
雄しべ
外側のオレンジ色のひらひらとしているのが、ハスの花の雄しべです。
特に花托と雌しべの形はユニークでおもしろいです。
また、雄しべが短かく雌しべに届かないので、自家受粉ができないようです。
なので、虫たちにお願いしているみたいですよ!
受粉が成功したら、雌しべの黄色のところは、茶色へと変わっていきます。
受粉は昆虫?

ハスの花に飛んできた、ハチです。
ハスの花は蜜がないので、香りで昆虫をおびき寄せてるようです。
ハスの花の香り嗅いだことありますか。
近くに寄らないとわからないのですが、ふんわりやさしい香りです。
大きなハスに顔を近づけてみると、甘い上品な良い香りがしますよ。
花托から果托へ

花が散ってしまい、雄しべも次第に枯れてしまうと花托(かたく)は、果托(かたく)へと変化していきます。
花びらが落ちた後の果実を乗せているのが「果托」と言われていますが、花托と果托は、混同されているような感じもあります。
どちらも呼び名は「かたく」ですね。
果托の内部では種が育っていきます。
ハスの種が成長していきます。

ハスの花の中は種づくりへと、
ハスの種が、ころっとしてきた感じです。
もしかしたら食べごろでしょうか?
ハスの種は日本ではあまり馴染みがないですが、ハスの種にはとても栄養があって味もよいです。
でんぷん質が豊富で、ちょっとトウモロコシに似ている食感です。
食用にする種は、花が咲いてから3週間ほどで収穫します。
果托に空いた穴から1つ1つ、緑色の実を取り出していきます。
収穫した実は、日陰干しで乾燥させ、密閉容器に入れて常温、または冷蔵で1ヶ月くらいは保存できるそうです。
ハスの根はレンコンとしてよく食べますが、花から根っこまで食用にされている植物です。

時間と共に種はどんどん乾燥して固くなっていきます。
蓮の実がなる果托に穴が空いているのは、空気を吸う為のものです。
根が水の中にあるため、果托を通して外から酸素を取り込みます。
そのため、果托の穴はそのまま根に直結してつながっています。
乾燥した果托

乾燥した果托は、水分が蒸発して穴だらけに見えます。
ひとつの穴に一つづつ種が入っています。
ハスの種は、とても寿命が長いそうです。
「大賀ハス」呼ばれてるハスは、2000 年以上前のものと推定されるハスの種からの育てられたハスです。
(株分けされたものが、各地で植えられています。)
また、この果托がまるでハチの巣みたいなので、「ハチス」⇒「ハス」と、呼ばれるようになったとも言われていますよ。
こげ茶色になった乾燥された果托は、インテリアや手芸などでも使われるのを見かけたりしませんか。
ハスの花からはちょっと想像の出来ない形ですが・・・面白いですよね。
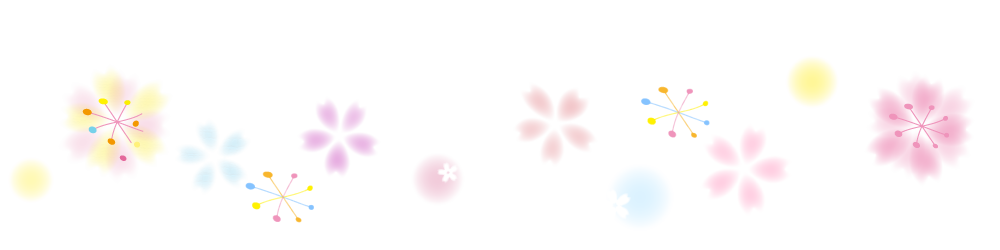




















[…] 何だろうと調べてみたら花托と言うそうです:詳細はこちら […]